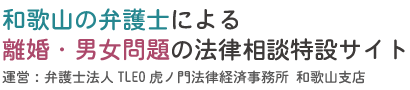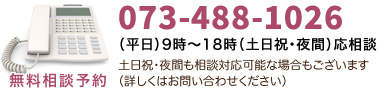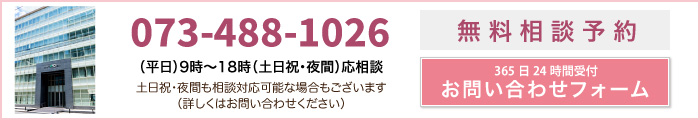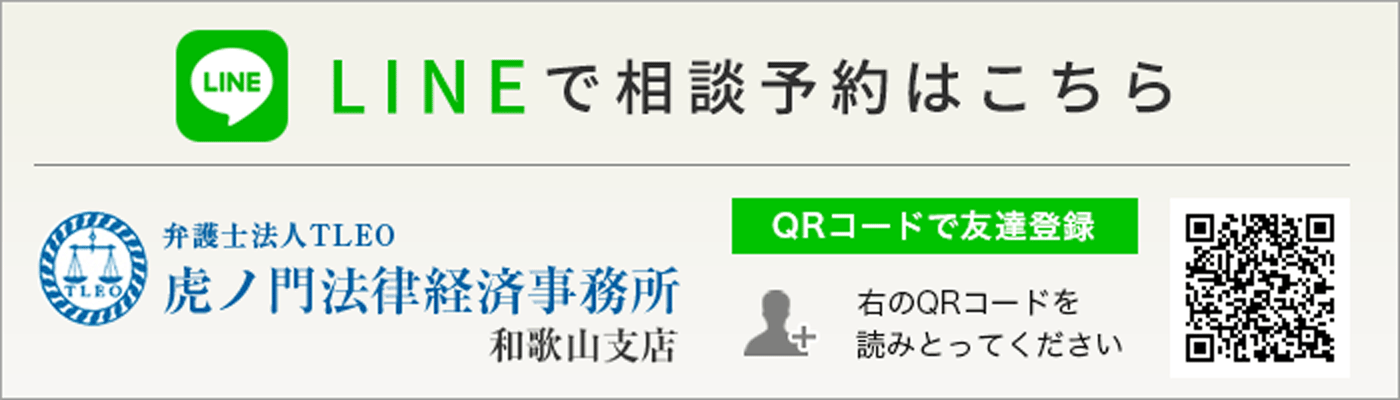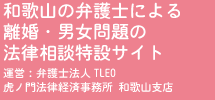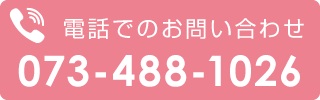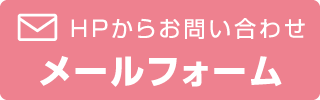はじめに
離婚や別居が進行する中でも、特に婚姻費用の金額をめぐる問題は当事者間で意見が対立しやすい問題です。そして、婚姻費用の計算は家族構成や収入によって大きく変わってきます。中でも、双方とも収入が高額な世帯の場合は、標準的な世帯とは異なる要素を考慮する必要があり、計算方法がより複雑になることがあります。
高収入世帯の婚姻費用計算の特殊性
高収入世帯の場合、子どもの教育費や習い事にかける費用が一般的な世帯と比べて高額になる傾向があります。たとえば、私立学校への通学や、複数の習い事を掛け持ちしているケースが多く見られます。このような場合、婚姻費用の計算において、これらの教育関連費用をどのように扱うかが大きな争点となります。なぜなら、これらの費用は一般的な生活費とは別枠で考慮される可能性があるためです。そのため、標準的な算定表による計算に加えて、追加の調整が必要になることがあります。
習い事・私学の費用が婚姻費用に与える影響
子どもの習い事や私学の費用は、別居前から継続して行われていた場合、婚姻費用の計算において重要な考慮要素となります。特に注目すべき点は、公立学校の平均的な教育費を超える部分についての取り扱いです。この超過分について、双方の収入に応じた負担を求められる可能性が高くなります。そのため、月々の婚姻費用の金額が、標準的な算定方式による金額から大きく変動することがあるのです。
当事務所で扱った婚姻費用の事例
当事務所で取り扱った事例では、依頼者の年収が約1350万円、相手方の年収が約725万円で、小学生と未就学児の2人の子どもがいました。子どもたちは、ピアノ、そろばん、水泳、学習塾など、複数の習い事に通っており、これらにかかる費用は月額で約14万円にも及んでいました。このような状況で、裁判所は婚姻費用の金額をどのように判断したのでしょうか。
婚姻費用への習い事の費用の加算方法
婚姻費用の算定において、裁判所は、双方の収入を前提に標準的な算定表を参照し、月額22万円から24万円の範囲内が相当であると判断しました。しかし、これは習い事の費用を含まない基本的な婚姻費用の金額です。習い事の費用を含んだ婚姻費用の算定には、まず基礎収入を計算する必要があります。この事例では、依頼者の基礎収入が約526万5000円、相手方の基礎収入が約297万2500円と算定されました。
基礎収入の求め方についてはコラム『再婚・養子縁組による養育費減額のポイントと計算方法』をご覧ください。
習い事や私学の教育費が婚姻費用に加算されるケースでは、通常の婚姻費用の算定方法に追加の基準が設けられることがあります。とくに、どの程度の超過分が妥当かについては複数の考え方が存在し、それぞれの方法で結果が異なる場合があります。ここでは、教育費の加算方法について2つの考え方を詳しく解説します。
2つの計算方法について
学校教育費が標準を超える場合の計算方法には、主に2つの考え方があります。ただし、いずれの方法でも、原則として義務者(支払う側)が超過分の負担に同意していることが前提となります。1つ目の考え方は、公立学校の平均的な教育費を超過した額を基礎収入で按分する方法です。2つ目は、子の生活費指数(62)のうち、学校教育費の生活費指数分(11)を超過する額を基礎収入で按分する方法です。
婚姻費用算定の際、高額な教育費をどのように負担するかについては、大きく分けて次の2つの方法が考えられます。
- ① 公立学校の平均的な教育費を超えた分を基礎収入で按分
この方法では、私学や習い事の費用が公立学校の平均的な教育費を超える場合、その超過分をそれぞれの収入に応じて按分し、負担割合を決める方法です。 - ② 子の生活費指数のうち、学校教育費に対応する指数を基準に按分
子どもの生活費指数(62《※1》)から、教育費に対応する部分(11《※1》)を基準として、教育費の超過分を算出する方法です。
※1
15歳未満の子どもの場合です。
本事例での計算方法
当事務所が取り扱った事案では、2つ目の考え方が採用されました。この方法での計算手順は以下の通りです。
具体的な計算例の解説
実際の計算では、まず、習い事の費用は月額で約14万円、学校の納付金が月額で約1万5000円とし、基礎収入に応じて按分する形で計算が進められました。基礎収入の割合は依頼者が約65%、相手方が約35%とされ、以下の手順で計算されています。
- ① 算定表で考慮済みの学校教育費の算出
両者の基礎収入の合計に対して、生活費指数を用いて計算します。その結果、年間で約55万9300円(月額約4万6600円)という金額が導き出されました。
【(約297万2500円+約526万5000円)×(11+11)÷(100+100+62+62)=約55万9300円】 - ② 超過教育費の算出
習い事の費用(約14万円)と学校等の納付金(約1万5000円)の合計から、考慮済みの学校教育費(月額で約5万円)を差し引いて、月額10万7750円となりました。
【約14万円+約1万5000円-約4万6600円=約10万8400円】 - ③ 依頼者の負担割合
依頼者の基礎収入割合に応じて、約10万8400円×約65%=約7万円が、依頼者の負担とされ、最終的に月額22万円~24万円の婚姻費用にこの額が加算されることとなりました。
実務上の注意点
婚姻費用に関する協議や審判を行う際、高額な教育費が婚姻費用に加算されるかどうかは、事前の準備や理解が重要です。ここでは、婚姻費用算定における実務上の注意点について、具体的に解説します。
別居前の生活実態の重要性
婚姻費用の算定において、学校教育費の加算が認められるかどうかは、別居前の生活実態が重要な判断材料となります。具体的には、別居前から子どもが私立学校に通っていたか、習い事に通っていたかなどが考慮されます。また、これらの費用負担について、双方が同意(容認)していたかどうかも重要な要素となります。そのため、別居前の生活状況や教育方針について、できる限り具体的な証拠を残しておくことが望ましいと言えます。
習い事の費用加算による影響
婚姻費用の分担額を争う際には、標準算定方式による基本額に加えて、高額な学校教育費が加算されるおそれがあることを十分に認識しておく必要があります。本事例のように、基本の婚姻費用に加えて約7万円もの追加負担が生じる可能性があります。このような加算は、毎月の支払額に大きな影響を与えることになりますので、事前に十分な検討と準備が必要です。特に、複数の習い事や私立学校への通学を検討している場合は、将来の婚姻費用への影響も考慮に入れた判断が求められます。
まとめ
婚姻費用の算定において、子どもの教育費や習い事の費用が加算されるかどうかは、別居前の生活実態が重要な判断材料となります。当事務所で取り扱った他の事例では、別居前の生活実態に加えて、双方の収入や学歴、社会的地位等を総合的に考慮し、私立学校への通学費用等の負担を認める審判もありました。このように、標準的な婚姻費用に加えて相当額の教育費用が加算される可能性があることから、事前の検討と準備が重要です。
当事務所では初回相談料を無料としていますので、教育費を含めた婚姻費用の計算方法でお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。
私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。
経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。
不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。
全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。
財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。
対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。
一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。