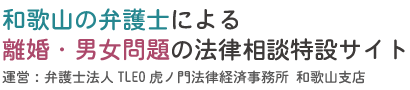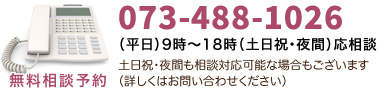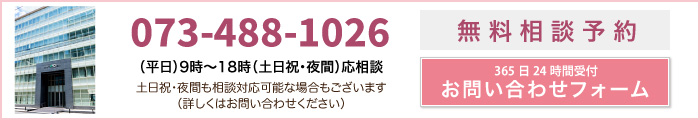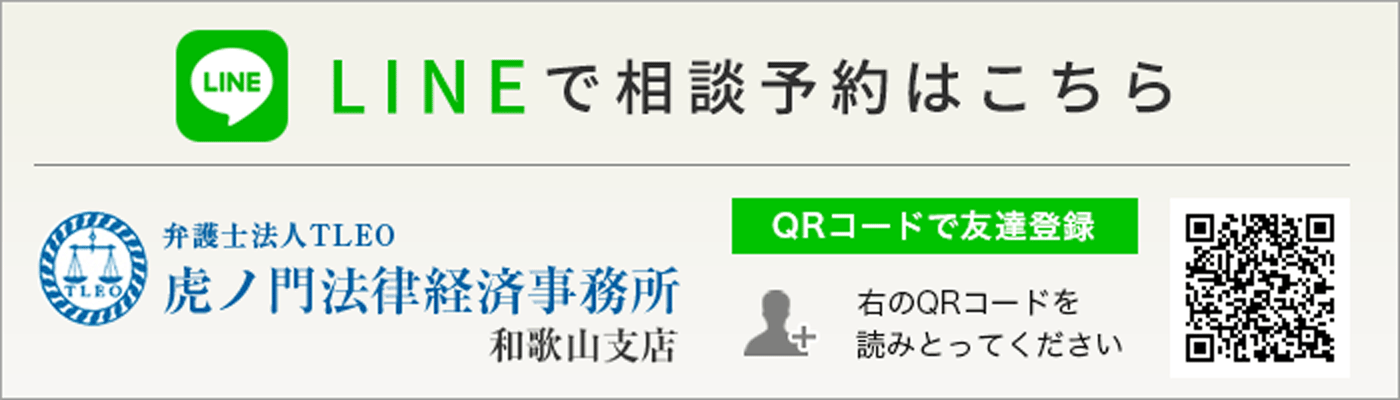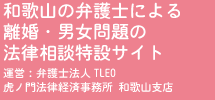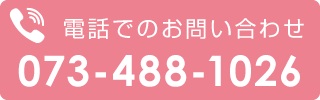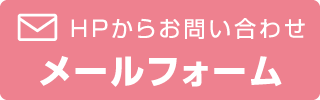はじめに
配偶者が障害を負い、障害年金を受給することになった場合、婚姻費用や養育費の算定にどのような影響があるのでしょうか。このような状況では、障害を持つ配偶者の生活維持と、子どもの養育費の確保という、受給者にとっても支払う側にとっても重要な問題が絡んできます。さらに、高度障害保険金を受給している場合は、その取り扱いについても検討が必要です。本コラムでは、障害年金や高度障害保険金を受給している方の婚姻費用・養育費の算定方法について、実例を交えながら詳しく解説していきます。
婚姻費用・養育費における障害年金の重要性
離婚・男女問題において、婚姻費用や養育費の算定は重要な課題となりますが、特に配偶者が障害年金を受給している場合は、慎重な検討が必要です。なぜなら、障害年金は障害者の生活を支えるための給付である一方で、家族の生活も支えるものでもあるからです。また、障害の程度や治療費の負担、自立のために必要な費用など、個別の事情を考慮する必要があります。このため、一般的な給与収入とは異なる特別な配慮が必要となり、その算定方法についても、独自の考え方が確立されています。
障害年金と高度障害保険金の基本と収入認定
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限される程度の障害が残った場合に支給される公的年金です。この年金は、障害者の生活を支えるための重要な収入源となっています。障害年金には、国民年金から支給される障害基礎年金と、厚生年金から支給される障害厚生年金があり、加入していた年金制度や保険料の納付状況、障害の程度などによって、受給できる年金が異なります。そして、障害年金は生活支援を目的としていることもあり、税金が課されない非課税の収入となっています。
通常の養育費・婚姻費用の算定表では公租公課(所得税・住民税・社会保険料など)が事前に考慮されているため、非課税の収入がある場合は、別の方法で養育費・婚姻費用を算定する必要があります。
高度障害保険金とは
高度障害保険金は、民間の生命保険契約に基づいて支払われる給付金です。これは、被保険者が病気やけがにより約款で定められた高度障害状態になった場合に支払われます。通常の生命保険では、死亡保険金と同額が支払われることが多く、障害者の経済的な生活基盤を支える重要な役割を果たしています。この保険金は、一時金として支払われる場合と、年金として定期的に支払われる場合があります。
高度障害保険金についても、障害年金と同様に非課税の収入となっています(所得税法施行令第30条第1号・国税庁「質疑応答事例」)。
障害年金と高度障害保険金は婚姻費用・養育費の計算で収入として考慮されるのか
結論から申し上げますと、障害年金も高度障害保険金も、婚姻費用や養育費の計算において収入として考慮されます。しかし、これらの給付は障害者の治療費や自立のための費用にも充てられるべき性質のものですので、その算定には特別な配慮が必要です。具体的には、障害の治療費や自立のための必要経費を特別経費として控除したり、標準的な医療費を超える部分を生活費として加算したりするなどの調整が行われます。また、保険金については、保険制度の趣旨を考慮して医療費の範囲を判断することになります。
障害年金と高度障害保険金受給者の婚姻費用・養育費の計算方法
基礎収入の計算方法
婚姻費用や養育費の算定には、基礎収入が重要です。基礎収入は、総収入から公租公課(所得税・住民税・社会保険料など)や職業費(被服費、交通・通信費、書籍費、交際費など)、特別経費(住居費用、医療費保険医療費など)を引いた額で算出します。障害年金受給者には通常の給与所得に比べて職業費がかからないため、職業費分を加算する調整が必要です。
職業費について
障害年金や高度障害保険金などの年金所得は、給与所得とは異なり、実際の職業費(被服費、交通・通信費、書籍費、交際費など)がかかっていません。しかし、婚姻費用・養育費の算定表や標準算定式は、給与所得者を基準に作られているため、これらの収入を給与所得に換算する必要があります。
『養育費,婚姻費用算定に関する実証的研究(令和元年12月23日、一般財団法人法曹会発行)』で年間収入別の職業費が発表され (平成25年から平成29年までの家計調査年報より推計)、全体平均で15.24%なっています。そのため、実務上では収入の15%を職業費として扱うことが多くなっています。具体的には、年金収入を0.85(1-0.15)で除して給与相当額を算出します(年金収入÷0.85=給与相当額)。
公租公課の扱いについて(非課税の収入の場合)
障害年金と高度障害保険金は非課税所得であり、通常の給与所得者が負担する公租公課(収入の8~35%)がかかりません。この点について、さいたま家裁越谷支部令和3年10月21日審判では、公租公課は考慮せず、職業費のみを考慮するという判断が示されています。
しかし、非課税所得であるにもかかわらず、通常の給与所得と同様の計算をすることは公平性の観点から問題があると考えられます。また、障害の種類によって医療費の助成制度や自己負担額の上限が異なることもあり、実際の生活費負担は事例ごとに大きく異なります。
当事務所で扱った障害年金等がある場合の養育費請求調停
事案の概要
当事務所で取り扱った事例をご紹介します。この事例では、妻から離婚と婚姻費用請求の調停依頼を受けました。夫は指定難病を発症し、無職の状態でした。夫の収入は、障害年金が年間で約280万円、生命保険会社からの高度障害保険金が年間で約170万円で、合計が約450万円でした。一方、妻の給与収入は約325万円でした。対象となる子どもは15歳以上が2人、15歳未満が1人の合計3人でした。この約450万円をそのまま給与収入として扱った場合、通常の標準算定表では養育費は月額6~8万円(下段)となりますが、職業費15%と公租公課22%※1(合計37%)を考慮して計算し直すと、夫の基礎年収は約715万円(約450万円÷0.63)となり、養育費は月額10~12万円(上段)と算定されることを主張しました。
※1
東京弁護士会「LIBRA 2017年8月号」より引用
結果
申立時には上記の月額10~12万円に、一番上の子どもの高等教育の学費を特別経費として追加で考慮し、月額16万円を請求しました。夫は子どもたちの将来を心配しており、話し合いの結果、月額14万円での合意に至りました。
まとめ
障害年金や高度障害保険金は、婚姻費用・養育費の算定において収入として考慮されますが、その計算方法には特別な配慮が必要です。特に、これらの給付が非課税所得であることや、職業費がかからないことを考慮した適切な換算が重要となります。また、障害の程度や医療費の負担、自立のための費用など、個別の事情によって必要な調整も異なってきます。婚姻費用・養育費の算定でお困りの方は、初回相談料は無料になっておりますのでお気軽に当事務所までご相談ください。

和歌山で離婚・男女問題にお悩みなら、虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店へご相談ください。
私たちは、あなたの「人生をやり直したい」という想いに、とことん寄り添います。
経験豊富な弁護士が、まずはお話をじっくりお伺いし、悔しいお気持ちやご希望をしっかりと受け止めます。
不倫の慰謝料請求、財産分与、親権・養育費など、複雑な問題もご安心ください。
全国ネットワークを活かした最新のノウハウと、粘り強い交渉力で、あなたにとって最善の解決を追求します。
財産分与に伴う税務や登記といった手続きも、税理士・司法書士等と連携し、ワンストップでサポートできるのが当事務所の強みです。
対応エリアは和歌山県全域。初回のご相談は無料です。
一人で抱え込まず、納得のいく再出発のために、まずはお気軽にお問い合わせください。